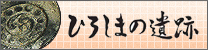令和7年度 発掘調査ニュース
(写真をクリックすると大きくなります)
神田遺跡(竹原市新庄町)
第2次調査終了
【調査期間】令和7年9月1日 ~ 令和7年12月26日
〔調査の概要〕

昨年度に続いて神田遺跡の発掘調査を行いました。調査は一般国道432号(竹原バイパス)道路改良事業に伴うもので、一般国道432号の東に隣接する南北約240m、東西約20mの南北に長い範囲が調査対象です。調査範囲を大きく3つに分け、北から1区、2区、3区と呼称しました。さらに各区は水路により南北に分断されています。調査面積は全体で約3,940㎡で、昨年度は1区北、1区南(一部)、2区南(面積は約2,400㎡)を調査し、今年度は1区南、2区北及び3区(面積は約1,500㎡)の調査を行いました。
1区南では、昨年度の第4遺構面に続く弥生時代の水田跡と考えられる畔状の高まりを確認しました。この高まりは、南側が後世の削平により欠失していました。第3遺構面では石列のほかに土坑2基、礎石1基、柵列と考えられるピット21基を確認しました。土坑内からは土師質土器が出土しており、これらの遺構の時期は中世以降と考えられます。
2区北では、第2遺構面から馬とおもわれる動物の足跡が多数確認されました。その下層では人の足跡が多数確認されたほか、南側で溝状遺構2基がみつかりました。
3区では、調査区北西から南東にかけて段状の高まりを確認しました。この高まりの北東側には平坦面がありましたが、遺構は確認されていません。高まりと平坦面の境には石列があり、下部には径50㎝以上の川原石を基礎として置いていることから、人為的に設置されたものと考えられます。南西側には畔状の高まりにより区画された、水田と考えられる耕作面が計6面確認され、人の足跡が500基以上確認されました。この耕作面は西から東への高低差が認められ、一部に水路と考えられる暗渠が設置されていました。また、北側の耕作面では柵列がみつかり、一部には杭の木材が残っていました。出土遺物には土師質土器のほか青磁や白磁などの中国製磁器があることから、3区の遺構は中世と考えられます。
2年に渡る調査の結果、神田遺跡の遺構は円礫を多く含む砂層の上にあることがわかりました。土層観察から、この砂層は河川の氾濫によって堆積したものと考えられ、遺構面の上にも複数回の氾濫による堆積が認められることから、遺跡は河川の影響を受けやすい立地であったことが明らかとなりました。今後、整理作業を行い、遺跡の性格等について検討していきます。

1区南 柵列・石列(北東から)

2区北 第2遺構面の様子(南から)
2区北 馬とおもわれる足跡(南から)
3区 水田と石列(空撮)
3区 石列(西から)
3区 石列の基礎(北西から)
3区南 水田と人の足跡(北西から)
3区南 柵列(西から)
3区南 柵列に残っていた杭
高屋堀2号遺跡(東広島市高屋町)
初年度の調査終了
【調査期間】令和7年10月20日 ~ 令和7年11月28日
〔調査の概要〕

高屋堀2号遺跡は東広島市高屋町高屋堀に所在します。遺跡は丘陵先端付近の北東から南西に向かって低くなる傾斜面に立地し、調査前は階段状の水田として整備されていました。南西側には萩原川が北西から南東に向かって流れています。
発掘調査は農業競争力強化農地整備事業の工事に伴うもので、今年度の調査面積は600㎡です。調査の結果、柵列跡(SA1~3)や柱穴を検出しました。SA1は約15mの範囲にわたって計57基のピットが並んでおり、西側は調査範囲外へ続いています。木杭の根本が残存しているピットもありました。SA2・3はSA1に近在し、SA1と同じ方向に伸びていることから、関連する遺構と考えられます。SA1のピット内からは土器が出土していますが、細片のため時期は特定できませんでした。しかし、周辺では青磁の口縁部片や土師質土器の鍋の口縁部片が出土しており、SA1~3が形成されたのは中世以降と考えられます。調査は来年度も行う予定です。

調査前風景(東から)

調査前風景(北西から)
SA1~3完掘(東から)
SA1 杭検出状況(北東から)
調査完了全景(南東から)
SA1作業風景(東から)
戸手古墳(神石郡神石高原町上豊松)
豊松地域初の古墳の調査
【調査期間】令和7年4月10日 ~ 5月2日
〔調査の概要〕

芳井油木線道路改良事業に伴い、発掘調査を行いました。調査面積は38.5㎡です。戸手古墳は北から南に延びる尾根の先端付近に立地し、標高約510mで、南の水田からの比高は約40mです。本古墳周辺は平地が少なく山がちな地形で、狭い谷沿いに水田が形成されています。
調査は道路改良工事の範囲内となる古墳の南側の部分と、その南側の部分から墳頂部に向かって設定した長さ8m・幅0.5mのトレンチ部分を調査しました。調査の結果、盛土はほとんど残っていませんでした。古墳は地山を整形して造られ、横穴式石室が築かれた墳頂部を中心に盛土がされたと考えられます。調査範囲ではないため発掘はしていませんが、横穴式石室の一部が露出しており、古墳の規模や性格を明らかにするため、調査前に地形測量と観察を行いました。その結果、本古墳は径12~13m程度の円墳で、現状で高さは約1.25mと推定されます。石室は地元で産出する石灰岩質角岩を使用して構築されていますが、天井石のうち原位置を保っていると思われるのは1枚のみで、他は北側に集石された状態で置かれていました。表面観察によると横穴式石室は無袖で、規模は長さ5.6m前後、幅は奥壁付近が約1.0mで、入口はそれより狭いと思われます。石室の主軸はほぼ南北方向を向いています。遺物は調査区西側から須恵器甕胴部の小片が数点出土しました。
調査範囲が限られていることや、出土遺物が少ないこともあり、古墳の時期ははっきりとしませんが、横穴式石室を持つことや須恵器が出土していることなどから、6世紀後半から7世紀前半と考えられます。

戸手古墳遠景
(空中写真・南東から)
戸手古墳全景
(空中写真・南から)
調査前近景(南東から)

横穴式石室(西から)

トレンチ調査風景(北西から)

調査区西部調査風景
(北東から)