|
どうやって作っていたの?
|
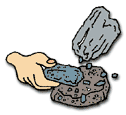 |
|
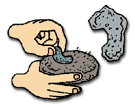 |
|
1.原石を粗くほどよい大きさに割っていきます。ハンマーは硬めの河原石を使います。おおよその形ができたら、次は石の端に押し付けて細かくはぎとり、形を整えます。 |
2.石の表面を磨いてきれいにしながら勾玉の形に近づけていきます。最初は目の粗い砥石(といし)、仕上げは目の細かい砥石を使います。背の部分を磨くには筋砥石と呼ばれる何本もの太めの筋が入った砥石を使い、腹側は内磨き砥石と呼ばれる棒状の砥石を使っていました。
|
|
|
|
||
 |
|
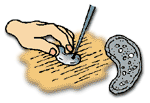 |
|
4.最後につやを出すために仕上げの磨きをして、ようやく完成です。
|
3.勾玉の形ができたところで、きりで穴をあけます。鉄のきりが使われるようになったのは弥生時代の終わりころで、それより前は石のきりで穴をあけていました。
|
 |
勾玉のほかにも,管玉(くだたま)や切子玉(きりこだま),棗(なつめ)玉,丸玉,小玉などさまざまな種類があります。 |
|||||||||||
|
 |
実際に玉に触ってみると,形だけでなく,石の硬さからも,作った人の「技術」の高さが想像できます。専門の技術者が集まって,玉を作った工房跡が全国各地で見つかっています。 中国地方では,島根県玉湯(たまゆ)町の出雲玉造(いずもたまつくり)遺跡が有名で,碧玉や水晶などの石を材料とした玉作りが行われていました。 |
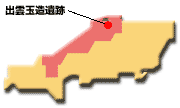 |
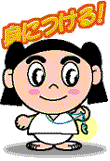 |
弥生時代には玉類の見つかる例が少ないため,ムラのリーダーや祭りを行う人など限られた人が身につけていたようです。 貴重な玉類を身につけることは,「美しさ」以上に,お守りとして,あるいは力の強さをアピールするための気持ちの表れと考えられています。 |
|
|
||||





